読みました『ニコライ二世とアレクサンドラ皇后 ロシア最後の皇帝一家の悲劇』

革命前のサンクトペテルブルグは「北のヴェニス」「雪のバビロン」と呼ばれ、イタリアの建築とフランスの調度によって壮大華麗に彩られていた。
人々はチャイコフスキーやボロディンを聞き、ドストエフスキー、プーシキン、ゴーゴリ、ツルゲーネフ、トルストイを読んだ。

ニコライ二世とアレクサンドラ皇后―ロシア最後の皇帝一家の悲劇
- 作者: ロバート・K.マッシー,Robert K. Massie,佐藤俊二
- 出版社/メーカー: 時事通信社
- 発売日: 1996/12
- メディア: 単行本
- クリック: 4回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
そんな中、皇帝ニコライ2世はスパルタ式の簡素さで育てられ、毎朝6時に冷水で体を洗い、農民服を来て質素な食事だけで夜8時まで執務に没頭した。
皇帝があらゆる決裁を行う伝統により、国際関係が複雑化して年々問題が山積した結果、朝から晩までその判断と処理に追われていたからだ。
無数の病院や孤児院を支え、また毎年殺到する請願にも応えた結果、毎年冬には皇室は一文無しになる有り様だった。
本書を読んで思うのは、運命とはまさにめぐりあわせだなということ。
ニコライ2世は、平時であれば本当に「良き人」だった。
しかし立て続けに4姉妹が生まれ、皇子を生むプレッシャーから皇妃アレクサンドラは精神を病んでしまう。
さらにようやく生まれた皇子は血友病だった。
藁をもつかむ思いの一家の相談相手となったラスプーチンに関する悪い噂が広がり、彼らをさらに悩ませた。
ある日の深夜、ドイツ皇帝から戦争を最終決断する書簡が届けられた。ロシアの判断如何によって開戦は避けられるかもしれない。
しかし彼は人が良すぎるが故に、スタッフを叩き起こしてアドバイスを求めることができなかった。
ひとり暗い宮殿の階段に座り込み、頭を抱えて夜明けまで悩み続けることしかできなかった。
結果、欧州大戦が勃発する。そして革命。
皇帝一家は共産主義者にとらえられ、ついに悲惨な最期を迎える。監禁の日々では警備兵の多くが同情的となり、彼らは一家の銃殺を拒否した。
その後、末妹アナスタシアをはじめ、子どもたちの生存説が各国でまことしやかに語られるようになる。
それは一家の哀れを感じた人々による幻だった。
また英国マウントバッテン卿は1979年に亡くなるまで、従妹でもある三女マリアの肖像を枕元に飾り、生涯その面影を追い続けた。
-
前の記事
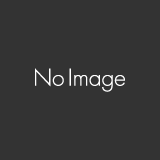
ネクスト私学出版記念パーティ(大阪) 2016.12.09
-
次の記事
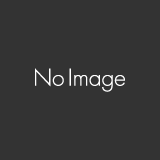
風企画忘年会 2016.12.23
