注文のこない料理店

近所にあるイタリア料理店があって、もう三年ほど前から気になって仕方なかった。仮にA店とする。
何が気になるかと言って、客が入っているのを見たことがない。
いや、たまにはある。あるにはあるが、それはゴールデンウィークとかクリスマスイブの夜とかに、ようやっと一組二組の客を見かけただけである。
このA店の主人、正しくは夫婦は、一体どうやって生活しているのだろうか?
そこで毎日、A店前を通りがかるたびに客の有無を確認したところ、厳密には月に5組ほど来店していることが判った。
しかしこれでは地代も払えまい。
叶姉妹のような謎の収入源があるか、霞を食らう仙人でなくては餓死する。
もちろんA店主は富豪でないだろう。
なぜなら店の前に誇らしげに、夫婦相合って協力し、艱難辛苦をともに乗り越えて脱サラして開店した旨、雑誌に取り上げられた際の切り抜きとして、大いに貼りつけているからである。
そしてA店の2軒隣に、同じようなイタリア料理店が去年くらいにオープンした。B店とする。
これがまた、いやみなくらいに大繁盛。
毎日毎日、どこからともなく老若男女が集結し、嬉しそうにランチやディナーで舌鼓の轟音を響かせているのだ。
私が件のA店主であれば、このB店を見れば悶死してしまうであろう。
店の入り口に血文字で「パスタ」とでも書いて。
つまり、たまのクリスマスイブに客を見かけたというのも、要はB店のおこぼれなのである。
無計画にやってきた若人が満員御礼に青くなり、身も心も寒くなる前にかけこんだのがA店だっただけのことだ。
「いずれ……行ってやらねばならん」
私は次第に、そう感ずるようになってきた。
深夜に通りがかると、夫婦はいつも店じまいの後、店にとりつけたテレビをぼけーっと眺めている。
会話しているのを見ないので、仲がいいんだか悪いんだか、うかがい知れない。
ここで解説しておこう。
なぜA店は閑古鳥が500羽ほど鳴き、B店は芋洗いのごとく混んでいるのか?
実は10年ほど前まで、A店はけっこう評判の店だったのである。
「あの店、行った?」
というのは、非常によく聞く会話のマクラであったのだ。
しかし国破れて山河あり。
要は、時代の波なのかなと思う。
B店は昨今はやりの食材、メニューを出し、店もオープンな雰囲気に演出してある。
厨房の様子は丸見えであり、壁材の色は明るく、照明は強め。
なるべく壁を廃して、植物などを使って間仕切りしてある。
実際に食べてみたが、味はまあまあだ。しかし雰囲気はよい。
対してA店は10年ほど前にはやった、「隠れ家」スタイルだ。
店内は外から見るにいかにも暗く、壁際に空きビンを意味なくぎっしり並べたりしている。
厨房カウンターにも所狭しと物をならべ、実に内向的である。
つまり味の問題ではないのだ。
みな、入店自体に足踏みしてしまうんじゃないか?
本当は旨いのに。勇気出して行けばいいのに。私もA店に行ったことはないのだが。
砂糖は甘い。しかし、甘いのが砂糖とは限らない。
味はいいが、外見が悪い。しかし、外見が悪いのは味がいいとはいえない。
それは理屈としては判るのだが、私は心中ふんぞりかえっているB店主の哄笑(実際は真面目で人の良さそうな店主)を思うにつけ、「やいやい、A店は味はいいんだぞ」と毒づくようになってきたのである。
店に入ったことはないが。
「仕方あるまい……」
私は決意した。
3年の月日は長かった。A店は、よくぞ今の今まで耐えた。
早くいかねば、本当に倒産する。
そして私は運命の扉を開けることにしたのである。
さて、昼の1時である。
店の前に立つ。
扉の横に「今日のスペシャルランチ」が掲げられている。さらに「OPEN」の札。
店を覗き見ると真っ暗である。
──おいおい、営業してるってのはウソだろう?
かといってランチならまだしも、夜の値段では食う気になれない。だがここで入らなければ、また3年の年月が必要になる。
はっきり言って、この店があと3年もつとは思えない。
世のため人のためだ。勇気をもって扉を開ける。
カウンターには真っ赤なTシャツを着た奥さんが、座って帳面を繰っていた。
その背中にはなぜか「好食中華」と大書されている(イタリア料理店なのに……)。
奥の厨房では、主人が何やら下ごしらえしている風であった。
主人が元気のない声で「いらっしゃい」という。
奥さんは無言で帳面を片づけ、無言のまま厨房に入ってゆく。
なんか、感じ悪いなあ。
店内は、意外にもちゃんと照明がついていた。
ただガラスに遮光フィルムが貼ってあり、しかも布のブラインドを下げてあったのである。
外から真っ暗に見えて当たり前である。
主人がやってきて、私の左側にまわりこんで水をおく。ああ、こういうのは右から割り込んだらいけないんだっけか。
メニューをひらく。主人、一度厨房へ戻る。
主人を呼ぶ。
主人は私の右方向からやってきたので、私は体を右に向けた。
すると主人はまたもや私の左側にまわりこみ、「ご注文は?」と私の背中に語りかけるのである。
変なこだわりだなあ。
ピザランチとパスタランチを注文した。
言うのを忘れていたが、1人で入ったわけでなくて夫婦で来たのである。
妻が不審そうに話しかけてきた。
「……空気が重い」
奥さんが中華料理風のシャツを着ているからだろうか。
いや、違う。
この夫婦に、一言の会話もないからだ。
無言で主人がピザをつくり、奥さんも無言でパスタをつくっている。
かなり分業が確立しているようだ。
でも客は私たちしかいないのだから、楽しげに、その、家族的というのか、アットホームな手作りのぬくもりでやってくれていいのである。
しかしふたりは目も合わせない。
離れたテーブルに、数年前にこの店を取材した雑誌が置いてあった。
ひらくと、同じレイアウトなのに店の色が全然ちがう。
今の店内はどんより暗い。
しかし数年前の写真は明るく、白っぽくて清潔感にあふれていた。
今だって埃があるわけではない。
しかし物が光をさえぎり(窓辺に訳のわからんギフト類がつまれている。こんなもん、奥に片づけとけよ)、長年の油アカが吹きつけの内壁にこびりついている。
埃がないってことは、ちゃんと掃除はしているということだ。
しかしそれは素人の掃除レベルであって、プロの掃除レベルではない。
まずミネストローネがやってきた。普通。
次いでサラダ。
市販のサウザンアイランド・ドレッシングがどっさりかけすぎにかかっている。
私はかつての阪神・淡路大震災の折り、救援物資のサウザンアイランドのサラダを毎日毎日食べたせいで、本当に申し訳ないことなのだが、今やこの味は吐き気をもよおす代物だ(当時みんなが食べないので、せっせと食べていた)。
そのため、サラダはもう食べることができなかった。
思えば、最近市販のドレッシングなんて食ってなかった。
彼女はアンチョビとレモンを使ったドレッシングを作るし、私も自前でごまドレッシングを作るのである(本来の意味で、ゴマスリの好きな私)。
メインがきた。
まず主人がピザをもってくる。今度も左側からかと思えば、なぜか右側から。
なんでじゃい。今こそ右から割りこまんようにせえよ!
次いで奥さんがパスタをもってくる。とっても無愛想。
しかも私たちは2人がけのテーブルがくっついて4人分になっている所に座っていたのだが、なぜかパスタを、そのくっついた「隣のテーブル」に置いていった……。わけがわからん……。
だが、味はどちらも意外に旨かった。
「おいしいね」
「うん」
あまりに重い空気に滅入りかけていた私たちは、この味でずいぶん生き返った……はずだった。
食べ進むにつれ、ふたりともどんどんお腹が重くなってゆく。
たかがこんな量で……おかしい……。
「ちょっと待って」
彼女が私を止める。
私は厨房に背を向けていたのだが、彼女はずっと厨房を見ていた。
主人が、新しいピザ生地をぺったんぺったん練っている。
そこには、ありえないほどの量のオリーブオイルがドボドボと練り込まれていた。
そうすると、ピザがジューシーなのにパリッと焼けるのだ。
パスタも、きっといいクリームを使っている。ねっとりとからみつく。
旨いには旨い。しかし……。
思えば、私はあまり腹が強くないのである。
彼女は油を使わずにトマトソースもミートソースも作るし、カルボナーラなんかだと、牛乳とコンソメと小麦粉で「なんちゃってクリーム」を作ってくれていたのである。
食べ終わった私たちは、お金を払って店を出た。
洞窟から抜け出たかのように、明るい日差しに目がくらむ。
腹が痛い。
私は彼女の、普段の料理に対する深い配慮に、心からお礼を言った。
「食ってる瞬間の味がいいだけじゃ、だめなんだなあ」
相田みつを風につぶやくと、私はお腹をおさえながら店を後にしたのであった。
(完)
-
前の記事
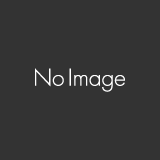
スカイマークで美青年を見た 2009.11.21
-
次の記事
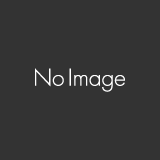
住所録:リストの表示について 2009.11.23
